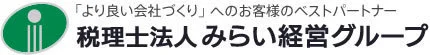Knowledge基礎知識
個人事業主が青色申告を行うメリット
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告は手続きがやや複雑ですが、税制上の大きなメリットがあるため、多くの個人事業主にとって有利な制度です。
本記事では、個人事業主が青色申告を行うメリットについて詳しく解説します。
青色申告とは
青色申告とは、一定の条件を満たすことで、税制上の優遇措置を受けられる確定申告の方法です。
青色申告では、課税所得から最大65万円(一定の要件を満たさない場合は55万円)または10万円の控除が受けられます。
また、青色申告の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得です。
青色申告の適用条件
青色申告を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。
・事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する
(開業後2ヶ月以内、または適用を希望する年の3月15日まで)
・帳簿および書類を一定期間保管する
(7年間または5年間)
・複式簿記で作成した損益計算書や貸借対照表を作成する
(最大65万円控除を受ける場合)
・電子帳簿保存またはe-Taxにより電子申告する
(最大65万円控除を受ける場合)
青色申告のメリット
青色申告を行うことで、以下のようなメリットを享受できます。
最大65万円の特別控除が受けられる
青色申告の最も大きなメリットの一つは、最大で65万円の「青色申告特別控除」を受けられることです。
所得から最大65万円を控除できるため、税額が大幅に軽減されます。
最大65万円の控除を受けるためには、上記の「青色申告の適用条件」のすべてを満たす必要があります。
このうち、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行わない場合、55万円の控除となります。
赤字を3年間繰り越せる
事業で赤字が発生した場合、翌年以降3年間にわたってその赤字を繰り越し、黒字と相殺することができます。
これにより、翌年以降の納税額を減らすことが可能です。
白色申告ではこの繰越控除は認められていないため、大きな違いとなります。
家族への給与を経費にできる
個人事業主が家族を従業員として雇用する場合、一定の条件を満たせば支払った給与を全額経費にできます。
これを「青色事業専従者給与」と呼び、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
白色申告の場合、家族への給与を経費とできるのは年間86万円(配偶者)または50万円(その他の親族)までに制限されるため、青色申告の方が有利となります。
30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる
通常、10万円以上の資産を購入した場合、減価償却で法定耐用年数にわたって経費計上されます。
一方で、青色申告を行うことで、「少額減価償却資産の特例」を活用でき、30万円未満の減価償却資産については購入年度に全額経費として計上できます。
一度に経費計上することで所得を圧縮できるため、その年の納税負担を軽減できます。
ただし、少額減価償却資産の特例は、年間300万円が上限となります。
貸倒引当金を計上できる
取引先が倒産したり、売掛金が回収不能になった場合に備えて、あらかじめ「貸倒引当金」を一定額まで計上することが可能です。
具体的には、売掛金や貸付金などの債権の年末残高に対して、5.5%(金融業の場合は3.3%)の額を貸倒引当金繰入として計上することが認められています。
この措置により、実際に貸倒れが発生したリスクを軽減できます。
青色申告の注意点
青色申告には多くのメリットがありますが、いくつかの注意点も存在します。
帳簿の作成が複雑
青色申告を行うには、複式簿記による記帳が必要となり、損益計算書や貸借対照表を作成しなければなりません。
簿記の知識がない場合、会計ソフトを利用するか、税理士のサポートを受けることが推奨されます。
ただし、10万円控除を選択する場合は、簡易簿記による記帳が認められており、貸借対照表の作成が不要です。
申請手続きが必要
青色申告を適用するには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
この申請を忘れると、青色申告のメリットを受けられません。
まとめ
青色申告は、個人事業主にとって大きな税制メリットを提供する制度です。
特に、最大65万円の特別控除、赤字の繰越控除、家族への給与の経費計上、少額減価償却資産の特例などは大きな利点となります。
一方で、帳簿作成の手間や申請手続きの必要性といった注意点もあるため、会計ソフトの活用や税理士のサポートを検討することをおすすめします。
青色申告について不安がある場合は、お気軽に当法人へご相談ください。