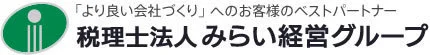Knowledge基礎知識
相続税の配偶者控除とは?注意点などを解説
相続税は、故人(被相続人)の財産を相続した際に課される税金ですが、配偶者には大きな税制優遇が設けられています。
それが「配偶者控除」です。
配偶者控除を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できるため、正しく理解し、適切に申告することが重要です。
本記事では、相続税の配偶者控除の仕組みや計算方法、注意点などについて詳しく解説します。
相続税の配偶者控除とは?
配偶者控除とは、相続税の計算において、配偶者が取得した相続財産のうち、一定額までを非課税とする制度です。
この控除を活用することで、配偶者が受け取る財産にかかる相続税を大幅に減らすことが可能になります。
配偶者控除の非課税限度額
配偶者が相続する財産のうち、以下のいずれか多い方の金額までが非課税となります。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額
たとえば、被相続人の遺産総額が3億円で、配偶者と子ども1人が相続人の場合、法定相続分は1/2(1.5億円)となります。
この場合、配偶者が1.5億円を相続しても、配偶者控除の非課税限度額1.6億円の範囲内であるため、相続税はかかりません。
なお、法定相続分とは民法が法定相続人に割り当てた分割割合です。
配偶者の法定相続分は、ほかの法定相続人に応じて変わります。
配偶者控除の適用条件
配偶者控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
配偶者が法定相続人であること
配偶者控除は、婚姻関係にある配偶者に適用されます。
内縁関係の配偶者(事実婚のパートナー)は、法的に相続人とは認められないため、配偶者控除の対象になりません。
申告時に戸籍謄本を提出し、法律上の配偶者であることを証明する必要があります。
相続税の申告を期限内に行うこと
配偶者控除を適用するためには、相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
また、申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内です。
この期限を過ぎると、配偶者控除を適用できなくなるため、注意が必要です。
遺産分割が確定していること
配偶者控除を適用するには、配偶者が相続する財産が確定している必要があります。
そのため、遺産分割協議がまとまっていない場合や、法的に確定していない状態では、控除を受けることができません。
配偶者控除の注意点
配偶者控除は非常に有利な制度ですが、適用にあたっていくつかの注意点があります。
二次相続の負担に注意
配偶者が相続税を大幅に軽減できるメリットがある一方で、将来的に二次相続の税負担が増加する可能性があります。
二次相続とは、配偶者が亡くなった際の相続のことを指します。
たとえば、夫の死亡時に全財産を妻が相続すると、妻の相続時に子どもが全財産を相続することになります。
この場合、配偶者控除が適用されず、課税対象となる財産が増えるため、子どもが支払う相続税が高額になる可能性があります。
そのため、一次相続(最初の相続)の時点で、配偶者と子どものバランスを考慮した分割を行うことが重要です。
分割方法については、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
申告漏れに注意
配偶者控除は、自動的に適用されるものではなく、相続税の申告を行うことが前提です。
たとえ相続税がゼロであっても、適用を受けるためには必ず申告書を提出する必要があります。
申告しなかった場合、控除が適用されず、本来不要な相続税を支払うことになってしまうため、注意が必要です。
遺産分割協議の長期化に注意
相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらない場合、原則として、配偶者控除が適用されません。
もし協議がまとまらない場合は、民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税を仮計算し、申告と納税をすることになります。
ただし、未分割の財産について「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、一時的に控除の適用を保留できます。
さらに、3年以内に分割が確定しない場合でも、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合は適用できる可能性があります。
救済措置があるものの、早めに遺産分割協議を進めることが大切です。
まとめ
配偶者控除は、配偶者の相続税負担を大幅に軽減できる強力な制度です。
1億6,000万円または法定相続分までの財産は非課税となるため、適切に活用することで大きな節税効果が期待できます。
ただし、二次相続の負担増加や申告漏れ、遺産分割協議の遅れには十分注意が必要です。
相続税対策をしっかりと行い、将来の負担を最小限に抑えるためにも、税理士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。